勾当台ってよく考えたら変な名前ですよねぇ。仙台に生まれた時から住んでいて今まで普通に勾当台公園って呼んでいました。

ところで仙台には市街地を横断する三つの主な道路がある、
青葉通、
広瀬通、
そして定禅寺通。
青葉通はわかる、杜の都仙台だから。
広瀬通もわかる、広瀬川流れる岸辺〜♬
定禅寺通の定禅寺ってなんだ?お寺なんかどこにもないぞ。
昔はあったんです、しかも重要な場所に。
現在の勾当台公園の裏あたりに定禅寺というお寺がありました。それは青葉城から見て鬼門に位置する場所にありました…しかしながら明治になって…明治6年に廃寺なってしまったのです。
古刹(こさつ)定禅寺は京都三宝院の末寺で、永正年間(1504~21)に融済法印を開山とした真言宗であった。
伊達政宗が仙台開府に当り、城の鬼門にあたるので、真言密法の祈願時として定めた。寺領六十六石を給して着座格に列し、仙台における真言宗三寺の一として重きをなした。住持はしばしば藩主の連歌の席に連なるなどのことがあり、伊達家の帰依も篤かったが、宝永五年(1708)正月の大火に堂宇がことごとく炎上した。さらに明治維新後は藩の外護(げご)を失って衰頽(すいたい)し、かつ明治六年に至り仙台鎮台病院をここに移すことになったので、ついに廃寺となった。定禅寺跡には戦災(昭和二十年七月)の時まで、古木として有名な定禅寺桜があった。
定禅寺通は本材木町からこの定禅寺門前に突き当たる通りということから起った地名である。
(仙台地名考 菊地勝之助著より)
定禅寺に続く道として定禅寺通という名が残ったのです。定禅寺は現在の勾当台公園の裏の方にあったそうです。
で、危なくスルーするところだった勾当台公園の勾当台、よく見ると変な漢字の集まりですね。勾は勾配の勾?当はあ当る?台は公園の奥が高台になっているが…。よくわからない。
調べてみると、勾当とは盲官の位階の一つで、上から検校、別当、勾当、座頭の順でした。
(※盲官:盲人で琵琶・管弦・鍼・あんまなどを業とした者に与えられた官名。)
座頭市は座頭の市さんだったんですね、なるほど。
勾当台とは花村勾当という盲人の狂歌師からきた地名だそうです。
花村勾当の屋敷があった場所で芭蕉の辻から見て高台であったため勾当台と呼ばれるようになったということです。確かに公園の奥、野外ステージがあるところは急に高くなっている。屋敷は現在の公園の東側から北側の高台にあったそうです。
花村勾当という人物は
ある時伊達政宗に名前を尋ねられると
「なに一字 ちがいありとて ことごとし きみは政宗 われは政一」
と即興の歌で答えた。この粋な返しにとても気に入った政宗は、その狂歌の才を愛でて、勾当の役職と屋敷を与えた。
現代だったらこのステージに上がってうたうのか(笑)ある意味聖地?

不思議な地名を紐解くと意外なおもしろいことがわかりますね。
ちなみに現在の勾当台公園は以前ブログに書いたように、地下鉄の開通に合わせて道路を作るために削られました。
削られた…、正確には分断されたのです。
昔の航空写真を見ると南西角の部分が今もなお残っているのです。
それはどこかというと毎年光のページェントで定禅寺通りの角に聳え立つ木に大きな(au協賛の)電飾がつけられてますよね、その木こそが以前の勾当台公園の南西角にあったヒマラヤシーダなのです。場所は変わっていません。
昭和50年の勾当台公園

昭和59年の勾当台公園(地下鉄南北線工事の様子)

現在の勾当台公園

今年の冬はまた違った感じで光のページェントを見ることができそうです。
【おまけ】
勾当台公園の一部には「古図広場」というところがあって昔の養賢堂の門の前に位置します。またそこには昔流れていたという四ッ谷用水の復元水路があります。単なる憩いの池じゃないんですよ。
古図広場という名だけあって林子平の銅像があったり、昔の通りの名前の地図があったり、また仙台城下をイメージした立体的な地図があります。ちょうどバスの停留所の裏、もしくは地下鉄の出入り口にあるので人は通るのですが通り過ぎる人がほとんどです。ちょっと立ち止まってちょっとの間、昔の風景を思い浮かべてはいかがでしょうか。


勾当台とはいかに
2013/12/5

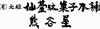



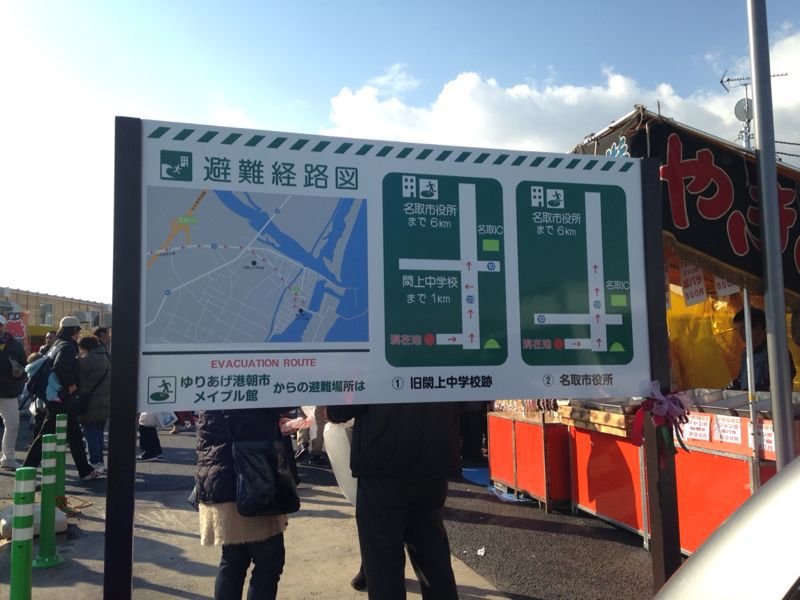




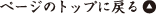

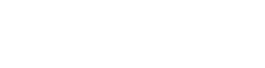
 オンラインショッピング
オンラインショッピング
コメント (0件)
コメントする